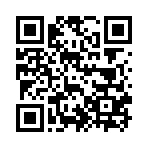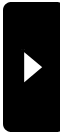2017年09月23日
『子どもの発達と描く活動』(新見 俊昌)

先日、現役時代に敬愛していた保育の先輩から 『この本知ってる? まだだったらいい本だから是非・・・』 と紹介してもらった、これまた私の尊敬する 新見俊昌さんの 『子どもの発達と描く活動』 という本
図書館 近くの本屋さんに行ったけど見つからず、アマゾンで購入しました(新見さんの推薦帯が付いた 中山ももこさんの 『絵を聴く保育』 も一緒に購入しました)
保育(子育て)に関する本は選ぶのに苦労するほど沢山出ていますが、新見さんの “描く” という行為からの実践・事例に基づいた理論は説得力もあり理解しやすく大好きな先生の一人です。(もう だいぶご高齢になられると思いますが)
一気に読み終えて、今すぐでも沢山の子ども達のいる保育現場にもう一度もどってみた~いなぁ、と一番に感じました。
若い頃は 教えてもらったことを実践してみる、あこがれの先輩たちの保育を真似てみる、色んな本や講習会で理論を学んでみる、失敗や試行錯誤を繰り返しながら無我夢中で過ごした毎日でした。
いまも、色々な本を読み返してみたり、新たな情報に巡り合ったり、その頃を振り返ったり、おやこリズムでの出来事と重ね合わせたり、自分なりに保育と言うものを考えてみている日々です。
そんな時に、この本を読んでみて “あぁ これはそう言う事なんだよねぇ” など今まではしっくりこなかった事がスッと腑に落ちてくる、理論と実践が体系的に整理され “目からうろこ” の世界、何か今やっていることにお墨付きを貰えたような安心感が湧いてきました。
実は、この先輩の保育の実際も一例として取材され本書に取り上げられています。
情報化の時代、理論(理屈)優先になったり 子ども達が主役でない保育(子育て)になってしまったりしていませんか?
色んな保育の実際を知り、自分たちの保育実践と対比(理論的に)してみる事は 保育に携わっている方たちにとって大変有意義なことだと思いますし、今後の活動の自信の源にもなって行くのではないでしょうか
保育の現場におられる方、育児真っ最中のお母さん方、私もすごくいい本だと思いますので機会があれば是非一度読んで頂けたらと思います。
本書の内容の要約はとても出来ませんので、ごく一部を
『子どもが絵にこめたお話を聞き取り 対話するということは、ただ子どものお話を聞いて書き留める事ではありません
保育者の願いを込めた対話であり、お互いの感性のひびき合い・・・・
子どものお話のどこに共感し、どう言葉を返していくのが大事・・・』
中山ももこさんの本は、高知県での地域に根ざした保育実践を中心にした本で、こちらも読んでゆくと楽しくなってきます。
Posted by リズムっこ at 19:19│Comments(0)
│日々雑感
※このブログではブログの持ち主が承認した後、コメントが反映される設定です。